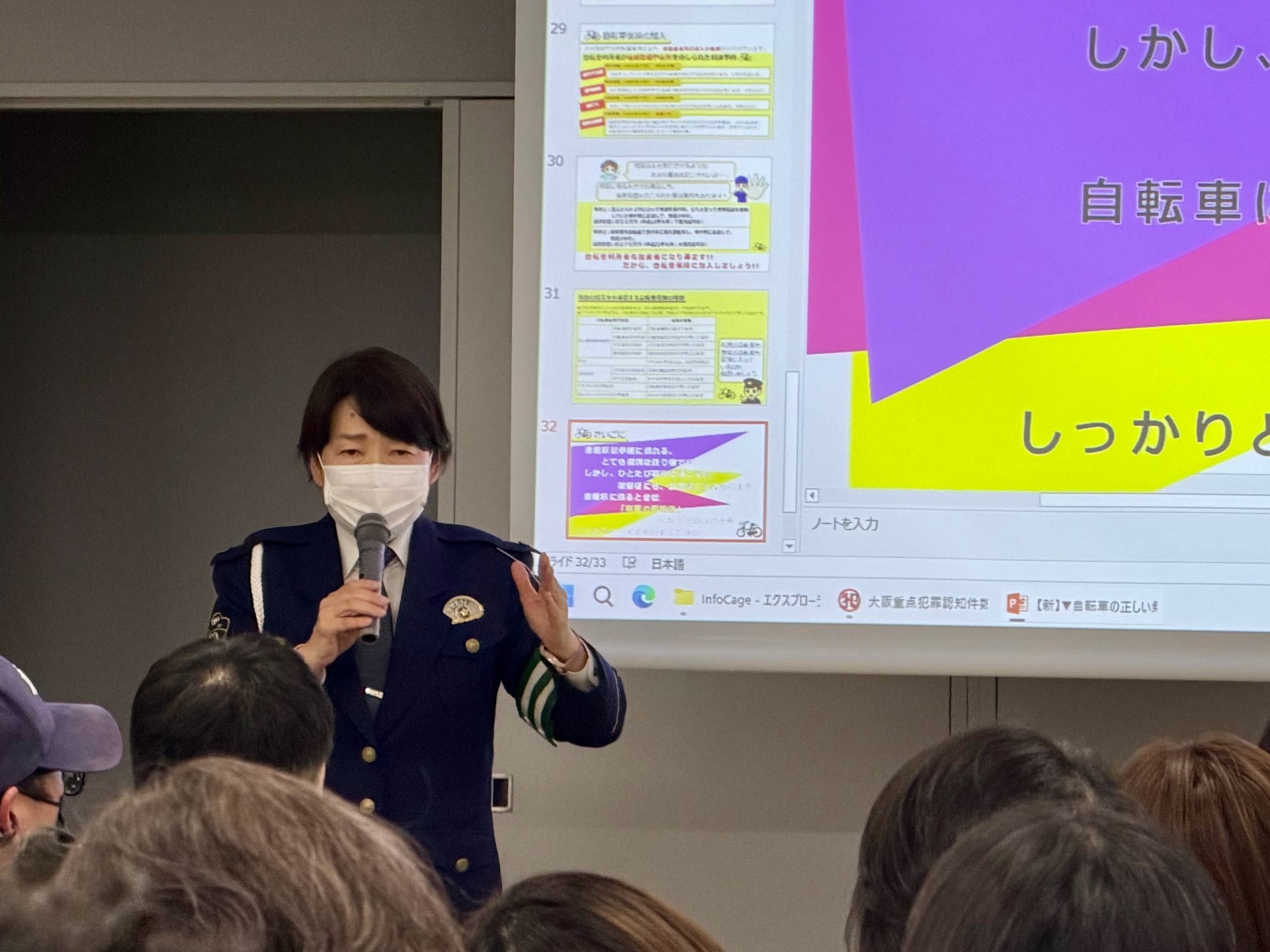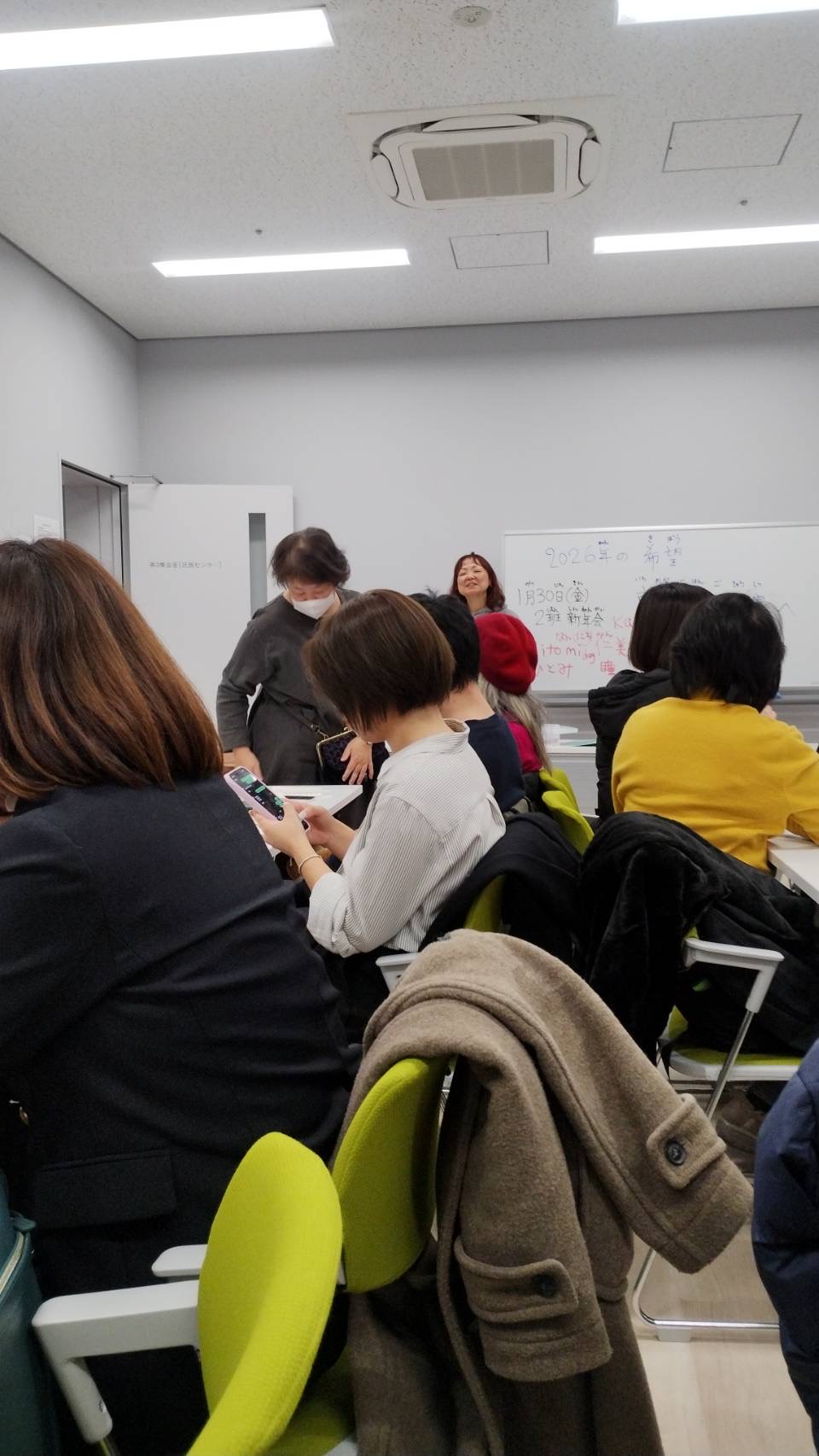2026年2月13日(金)
最近「空気」について気になるので書いてみます。
日本でいう「空気」とは、部屋の雰囲気や人間関係、その場の流れのことです。日本では、思っていることを全部言葉にするよりも、「今はどう言うのが無難か」「相手は何を求めているか」を考えて発言することがいいとされてきました。
たとえば、何かを断るとき。
日本では「できません」とはっきり言わずに、「ちょっと難しいですね」「今回は見送ります」と言うことがよくあります。日本人同士なら「これは断っているな」と分かりますが、外国の人にはとても分かりにくい表現です。「可能性はまだあるの?」と本気で期待してしまう人もいます。
学校や職場では、「周りに合わせる」「目立ちすぎない」「迷惑をかけない」ことが自然に求められます。これは、集団の中でうまくやっていくための知恵でもありますが、その一方で、自分の意見をはっきりと言いにくいと感じる時があります。
この空気を読む文化のおかげで、日本は比較的トラブルが少なく、静かで秩序のある社会になっていると思われる。ただし、それは暗黙のルールが共有されているからこそ成り立つもので、日本で育っていない人にとっては、「ルールがないのにルールがある」ように感じられることでしょう。
昔、仕事で「いいな」と思って黙っていると、外国の人に「なぜなにも言わないの?」と言われたその時は「???」でしたが、今考えると「すばらしい!」「良いことだ!」とはっきり言うべきだったと感じてます。
お互い何でも言い合える(程度はある)関係を築いていきたいと思います。